こんにちは、システムエンジニア歴30年のおかかです。
今回はちょっと妄想シリーズ。
「もし、世の中からSES(システムエンジニアリングサービス)がなかったら、どうなっちゃうの?」
って話をしてみます。
■ そもそもSESって何?
まず簡単におさらい。
SESは「エンジニアを時間単位で企業に常駐させて、開発や運用を支援するサービス」です。
ざっくり言えば「技術者レンタル」。発注側は人手がほしい、受注側は人を送り込む。そんな仕組み。
■ SESがなかったら、何が変わる?
もしSESが存在しなかったら…
- 即戦力が足りないときにどうする?
- 案件が増えても人を追加できない?
- エンジニアも転職かフリーしかない?
などなど、業界の動き方そのものが変わってきます。
■ 発注側と受注側、それぞれのメリット・デメリット
◆ 発注側(企業やSIer)
| SESありのメリット | SESありのデメリット |
|---|---|
| 必要なスキルを持つ人をすぐ呼べる | 社内にノウハウが残りにくい |
| リソース調整が柔軟 | 教育・マネジメントの手間がかかる |
| SESなしのメリット | SESなしのデメリット |
|---|---|
| チームが固定されて連携しやすい | 人材不足のときに即対応できない |
| セキュリティ・機密管理がしやすい | 新技術を取り入れにくいことも |
◆ 受注側(SES企業やフリーランス)
| SESありのメリット | SESありのデメリット |
|---|---|
| 案件が継続的に入ってくる | 「派遣感覚」で成長しづらい場合も |
| いろんな現場で経験が積める | 帰属意識が薄れていくこともある |
| SESなしのメリット | SESなしのデメリット |
|---|---|
| 自社でじっくりノウハウを貯められる | 営業力がないと仕事が取れない |
| チームとして成長できる | 案件の波に左右されやすい |
■ 海外ではSESってどうなの?
実は、日本みたいな「常駐型SES」は海外ではあまりメジャーじゃないらしいです。
- アメリカやヨーロッパ:基本は成果物ベースの契約
- フリーランス文化が根付いてる
- リモートワークが当たり前
つまり、「人」じゃなく「成果」で評価される世界。
その分、個人のスキルや実績がめちゃくちゃ重視されます。
■ 結局、SESって悪なの?
いやいや、そうじゃない。
SESがあることで、救われてるプロジェクトもいっぱいあるし、成長のきっかけになる若手エンジニアもたくさんいる。
でも、「SESでいいや」と思考停止すると、そこに成長はない。
■ おかか的まとめ
SESがなくなった世界を想像すると、エンジニアも企業も、もっと本気で「育てる」「任せる」覚悟が必要になります。
そういう意味では、「SESのない世界」は、ちょっとだけ理想かもしれないけど、現実的には“うまく使いこなす”のが大事かなと。
✍️ 最後にひとこと
「SESを使う理由」と「SESに頼る理由」は、似て非なるもの。
あなたはどっちの立場?

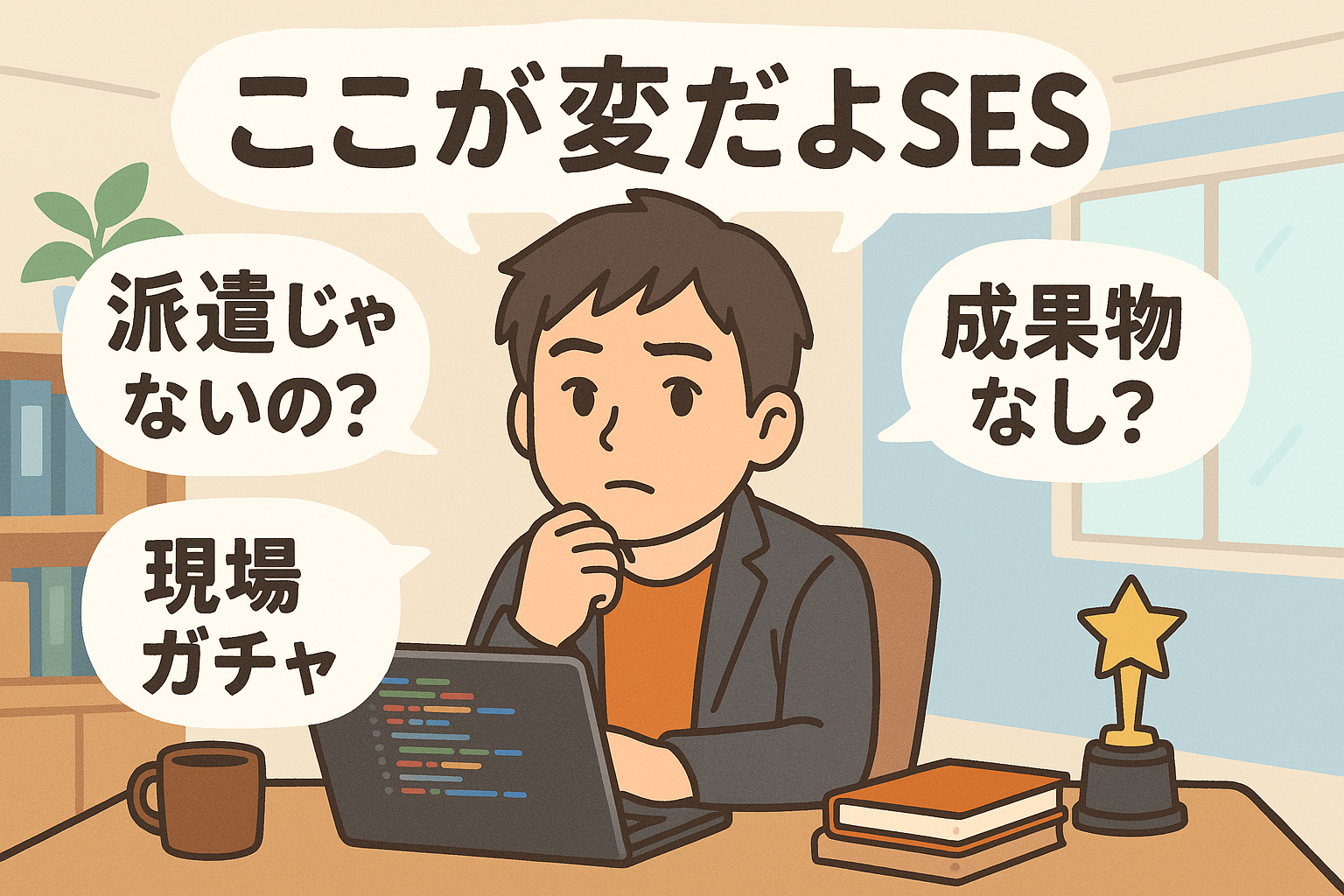
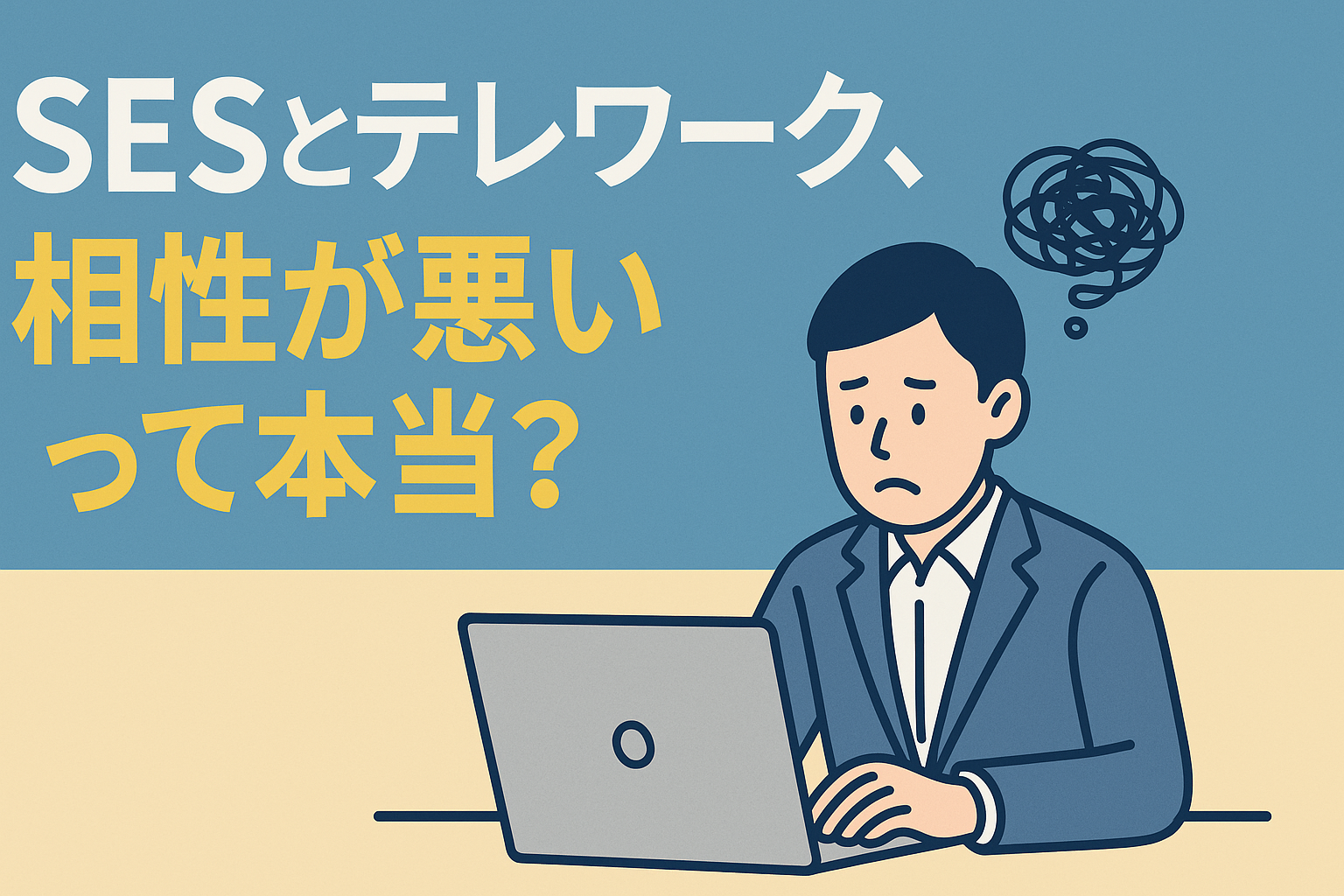
コメント