
あれは、こうで・・・
これは、ああで・・・

なんでそうなるのかな?常識的に考えたら分かるでしょ?
IT業界30余年、フリーランスのシルバーエンジニア。おにぎりです。
システム開発の現場でよく聞く「常識的に考えて」。
でもこの言葉、実はトラブルの火種になりやすいんです。
理由はかんたん。「常識」は人によって違うから。
そこで必要になるのが、“常識のすり合わせ”。
経験上、ここをサボるとチーム内の誤解や対立が起きがち。
この記事では、小さなチームでもすぐ実践できる「常識レベルの合わせ方」を紹介します。
- 『常識』の正体
- 『常識』がなぜ通じないのか
- 『常識』レベルの合わせ方
- チーム内ですぐできる工夫
お悩み:「言わなくても分かるでしょ」が通じない

同じ日本人同士なんだから、言わなくても分かるでしょ?って思ってた…

『常識的に考えて・・・』『言わなくても分かる』
かなりトラブルを招きやすい考え方だね。
この現場で通じない『常識』について、考えてみよう。
常識のズレを防ぐには?まず“合わせられる仕組み”を作ろう
『常識』は”その人が過去に経験した世界”のこと。
人が違えば、『常識』も違うのは当たり前。
この『常識』を合わせられば仕事ははかどる
「常識」が通じない理由とは?実例で解説
たとえば、Aさんにとって「報連相」は当たり前でも、
Bさんは「聞かれたら答えるスタイル」が普通かもしれない。
同じ業界・同じ会社でも、育ったチームや文化でまったく違う。
つまり「みんな同じ常識で動いてる」は、幻想。
チームができた瞬間に、もう常識のズレがある前提で動こう。
チームで常識を合わせる3つのステップ
ステップ1:最初に「前提を言語化する」
- 例:「レビューは必ず上長に依頼」など、行動のルールを口に出し、資料に残す
- 資料に残しておくと、あとから参加した人にも伝わる

すごく当然のことなんだけど、この言語化ができていない現場やチームがとても多いんだ。
『最初は作っていたんだけど、今は使っていない』みたいに、ルールが形骸化しているってこともよくあるね。
ステップ2:「確認しやすい雰囲気」をつくる
- 質問されたときに「え?そんなの常識でしょ」って返さない(質問することを否定しない)
- チーム全体で“質問ウェルカム”を掲げる
ステップ3:「言いにくい違和感」を拾う
- 週1のふりかえりなどで「最近ひっかかったこと」を出し合う
- 小さい違和感を感じた時こそ、常識ズレのサインとして拾おう
「常識のすり合わせ」でチームが変わる!

「常識でしょ?」って言葉を減らしただけで、『常識違い』が無くなったよ。
なによりチームの空気が良くなった!
- 「当たり前」と思っているルールを3つ言語化してみる
- チームで「気になることを出す時間」を週1で設けてみる
チームの心地よさは、地味な「常識合わせ」から始まります。
気づいた人から、動いてみよう。
この投稿が悩んでいる人へのヒントになればうれしいです。
もし、ご意見や扱ってほしいテーマなどがあれば、気軽にコメントしてください!

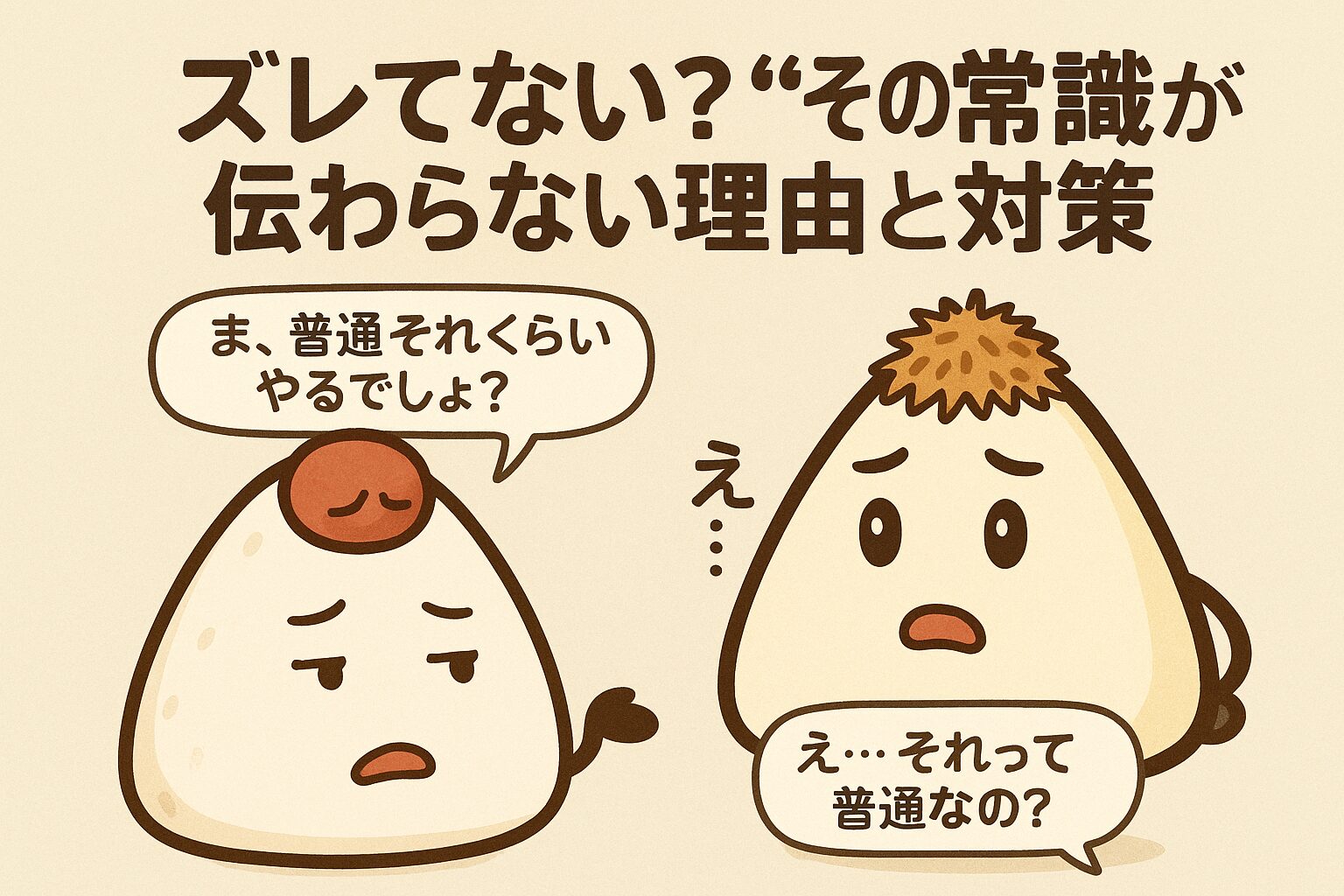


コメント