
おかかくん
え、結局どう作ればいいの?…これってこっちの責任?
こんにちは。IT業界30余年、フリーランスのシルバーエンジニア。おにぎりです。
「ざっくりこんな感じで、あとはよろしく」
そんなふうに曖昧な要件を丸投げされた経験、ありませんか?
気づけば設計も実装も自分の判断に。しかも納期はそのまま。
でも安心してください。若手でも今日から使える具体的な対処法があります。
今回は、要件が曖昧なまま押し付けられる背景と、
若手でもできる対処法をお伝えします。
要件のモヤモヤをクリアにして、納得して進められる開発を目指しましょう。
この記事の結論
お悩み:曖昧な要件は「見える化」して先手を打つ

おかかくん
要件も資料もあやふやなのに…納期だけは厳守って言われた…

おにぎりさん
“分からないまま進める”のが、一番リスクなんだよ
あいまいなまま引き受けると、トラブルの温床。
聞きづらくても、明文化・仮決め・確認の3ステップが重要です。
わからないことを見える形にして、責任の所在を共有することがポイントです。
なぜ、要件が固まらないのか?
要件がふわっとしている背景には、発注側の事情があることも多い。
たとえば社内でまだ承認が下りていない、仕様が頻繁に変わる…など。
ただ、それに巻き込まれてしまっては、エンジニアが疲弊してしまう。
だからこそ、「聞く勇気」より「聞かないリスク」の方が大きいと知っておこう。
対処方法:3つのステップで『不明』を『明確』に
ステップ①:グレーな指示に質問を返す
- 「誰が」「何を」「どんな条件で」を分解して聞く
- 例:「通知が飛ぶように」→「誰に、どんな内容を、いつ?」
ステップ②:不明点は「仮」で書き起こす
- 不確定な内容は「現時点の前提」で文書化
- 例:「AパターンとBパターン、今回はAで進めます(要確認)」
ステップ③:「見える化」で責任共有
- 要件定義書や設計書に「要確認」「未確定」のマークを明示
- 「レビュー時に確認します」とひと言添えるだけで違う
まとめ:小さな確認を積み重ねること

おかかくん
ちゃんと見える化して、話せるようになった!これならいけそう!
曖昧な要件をそのまま受け取るのは、事故のもと。
でも、「聞く力」と「文書化する工夫」があれば、防げます。
まずは今のプロジェクトで、“あいまいな部分”を書き出してみましょう。
わからないまま進めず、小さな確認を積み重ねることが
エンジニアとしての信頼にもつながりますよ。

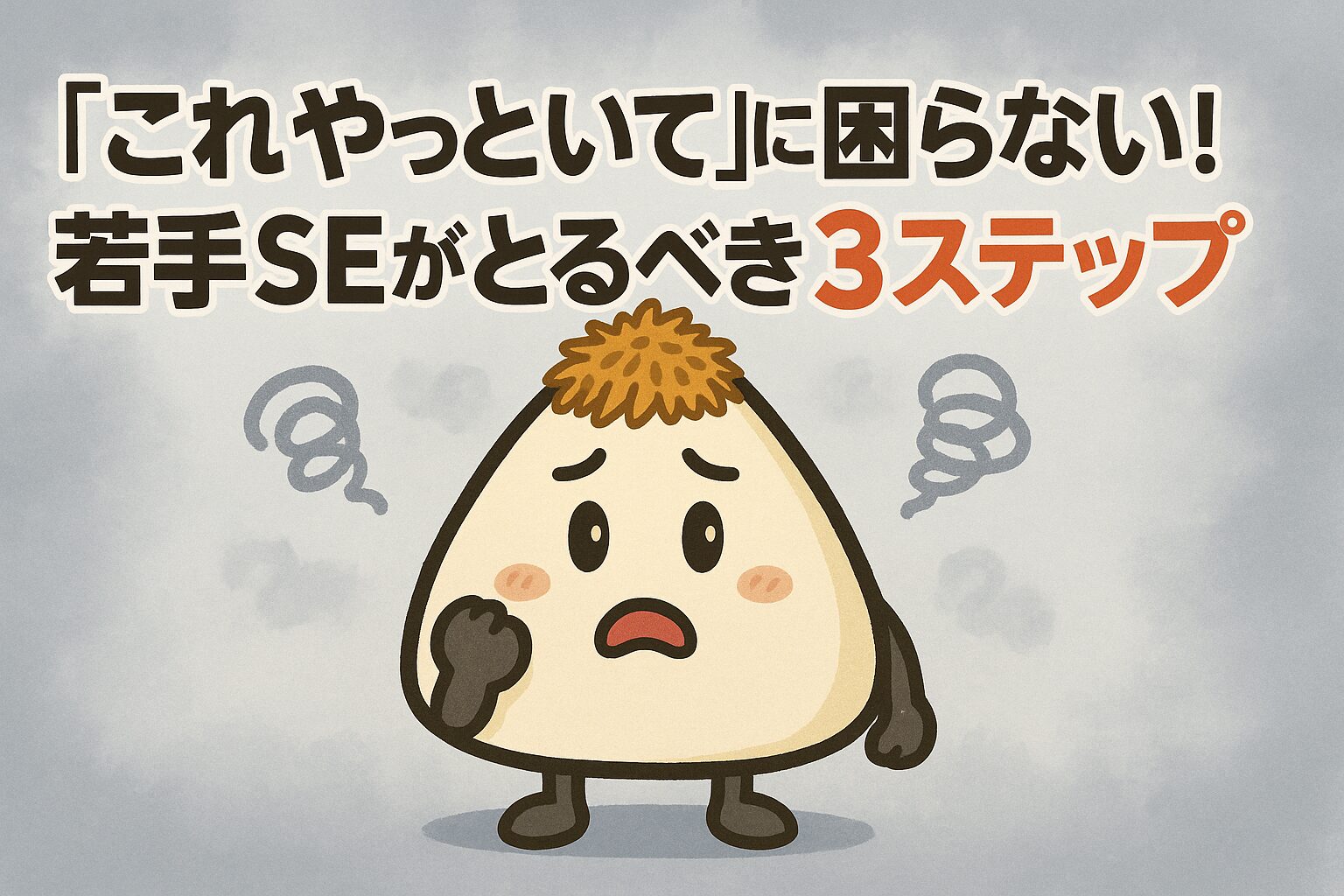
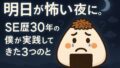

コメント